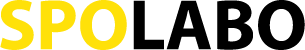今が旬!!アンコウの栄養と効果。
見た目はグロテクスですが、栄養豊富なアンコウ。骨以外に捨てるところがないと言われています。今回はアンコウの栄養と効果について纏めました。
特徴
大きさが70cm~1mにまで成長する大型種。水深30~500mの海底に生息しています。北海道以南のインド・西太平洋行きに棲む。水温は17~20℃までの低温を好む傾向があるが、12℃以下になるとほとんど生息せず、極度の低温は好まない。アンコウは手足のように変形したヒレで這うように海底を移動している。肉食性で、低底魚や甲殻類などを捕食する。海底の砂に潜り、頭についている突起(背びれの棘が変化した「疑似餌」)の先をひらひらさせて小魚を誘い、エサだと思い寄ってきた魚を丸呑みにする。産卵期は4~6月。市場への入荷量が多いわけではないが、値段は安いのが特徴のようです。
あん肝とは
あん肝とは、あんこうの肝臓です。
あんこうはエサの少ない深海に生息しているため、少ない栄養を脂肪として肝臓に蓄える性質があります。そのため、あんこうの肝は濃厚でまろやかな味わいとなり、まるでフォアグラのような高級感のある仕上がりになります。あんこうの身はあっさりとした淡白な味わいで低脂質高タンパクな食材ですが、あん肝は脂質が多くビタミン・ミネラルも豊富に含みます。
栄養と効果
①ビタミンD
あん肝はビタミンDが豊富です。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進してくれる働きがあり、骨粗鬆症の予防に役立ちます。あんこうの身100gあたりにに含まれるビタミンDは1.0μg、ビタミンDが豊富であるといわれている鮭でも33.0μgですから、あん肝のビタミンD含有量110μgがいかに多いかがわかります。ビタミンDは脂溶性ビタミンであるため、脂質を多く含むあん肝に豊富に蓄えられているのです。
②ビタミンB2、ビオチン
ビタミンB2は体内で補酵素としてほとんどすべての栄養素の代謝に関わっており、エネルギーの代謝を高めます。そのため、疲労回復に役立ちます。また、ビオチンも糖質やアミノ酸、脂質の代謝に関わっており、ビタミンB2とともにエネルギー代謝を高めてくれます。さらに、ビタミンB2とビオチンをはじめとしたビタミンB群は、皮膚粘膜の正常維持の役割も担っており、口内炎や肌荒れ防止に効果が期待できます。
③ミネラル、ビタミンB12
鉄は赤血球の原料となるミネラルで、貧血の予防・改善には欠かせない栄養素です。また、銅は私達の身体の骨や骨格筋、血液に存在していますが、鉄とともに造血機能に関わっています。さらに、ビタミンB12も補酵素としてアミノ酸や脂質などの代謝に関わっており、不足すると悪性貧血を引き起こします。以上のように、あん肝には造血機能に関わる重要な栄養素である鉄、銅、ビタミンB12が豊富に含まれているのです。そのため、貧血や貧血を原因とするめまいや立ちくらみなどの症状を予防・改善するのに役立ちます。
骨以外に捨てるところはないと言われているアンコウ。栄養豊富なアンコウは鍋にもピッタリなのでこの冬に食べてみてはどうでしょうか?
関連するまとめ

水分補給は大事ですが、過剰な水分が悪影響をもたらす「水毒」とは
体が冷える、疲れやすい、手足がむくむなど、夏でもこういった症状に悩まされている方は、「水毒」かもしれません。…
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
アンケート特集
みんなはどう思っている?

顔だけじゃない…理想のカラダの男性有名人といえば?
スポラボ編集部 / 837 view

メタボ対策!?運動する頻度は?
スポラボ編集部 / 877 view

水分やミネラルなどを補給できるスポーツドリンク!飲む頻度は?
スポラボ編集部 / 842 view