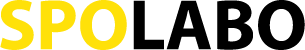冬は特に多い?冬の「むくみ」に効果的な食材
むくみは一年中現れますが、冬は特に実感することが多いそうです。マッサージやストレッチだけでなく食事からも予防法を考えてみましょう。
冬のむくみの原因
私たちの身体の中では、血液が滞ることなく流れているとリンパの働きや循環もスムーズに流れてむくみが生じることはありません。むくみの原因は、体内に水分が必要以上に溜まってしまい、この血液やリンパの流れが悪くなることで起こります。
冬の寒い季節には、気温低下の影響により筋肉がスムーズに動かなくなってしまい代謝が低下し、特に血液の流れが滞りやすくなることでむくみが引き起こされやすくなります。
代謝を上げて身体を温めよう!
冬場は外気の気温が低いのはもちろん、意識的に体を温めないと体温も低下してしまいます。また、冬は寒いがゆえに外出する機会も減り、行動範囲や活動範囲も夏場より減少する傾向があります。
基礎代謝は個人差がありますが、動きが少なくなることによって血液の流れも悪くなり、筋肉が硬くなって冷えやむくみとして体に現れます。
代謝を高める食材
しょうが
しょうがには、ジンゲロールとショウガオールという成分が含まれています。ジンゲロールは体の熱を末端に運ぶ働き、ショウガオールは熱をつくる働きがあります。
また、香り成分のガラノラクトンはジンゲロールと共に血液のすみずみまで運ばれ、細くなった血液循環の悪い末梢の血管を広げる働きがあります。しょうがを食べることで血液の循環がよくなると、発汗や利尿作用が働き、余分な水分が体から出ていきやすくなります。
唐辛子
唐辛子には、体を温めて発汗させる作用を持つカプサイシンが含まれています。キムチや麻婆豆腐の辛みはカプサイシンによるもので、体内に入ると血液によって全身に運ばれ、脳や脊髄などにある神経を刺激します。
その刺激が伝わり、アドレナリンが分泌されます。カプサイシンがエネルギーの代謝を活発にさせることによって、体温が上昇し、発汗が促進されます。
根菜類やイモ類
ごぼうなどの根菜類や里芋などのイモ類は水分が少なく、ビタミンCやビタミンE、鉄などをはじめとするミネラルを多く含むものが多くあります。
ビタミンEは血行促進作用、ミネラルはたんぱく質が体内で活用されるのに必須で、たんぱく質は血液や筋肉を作る素となり、体温を維持するのには必要不可欠です。また、根菜はスープや煮物など温かい料理で食べることがほとんどであることも、体を温めることに繋がっていると考えられています。
白菜
白菜にも根菜類と同じようにビタミンCが豊富に含まれています。血液の主要な材料となる鉄分の吸収を促進、毛細血管の機能を保持する働きがあります。
関連するまとめ
 大河原奈々未
大河原奈々未
地元横浜のスポーツチームをこよなく愛しています。
マリノスもベイスターズもビーコルも、頑張れ~
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

スポーツドリンクを購入!!選ぶポイントって何?
スポラボ編集部 / 916 view

すばやく疲労回復させる大豆ペプチド
スポラボ編集部 / 895 view

手軽に水分補給!!どんな時にスポーツドリンクを飲む?
スポラボ編集部 / 889 view