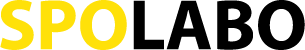季節の変わり目は要注意!その身体の不調は「寒暖差アレルギー」かも!
このところ、暑さも収まり、逆に肌寒い日も増えてきました。この時期は寒暖差が激しいことで、「寒暖差アレルギー」が起こりやすいので要注意です。
季節の変わり目に起こりやすい「寒暖差アレルギー」
「寒暖差アレルギー」は、寒暖の差により鼻の奥の毛細血管が詰まり、鼻の粘膜が腫れることで起きる鼻炎で、医学的には「血管運動性鼻炎」と診断されることがあるそうです。
主な症状として、鼻水・鼻づまりなど鼻がムズムズする、くしゃみが出る、じんましんが出る、イライラなどストレスを感じる、食欲減退や胃腸の不振などが挙げられます。気温差が激しいと、服装などの調節も難しくなり、上記のような症状が出ると風邪をひいたと思われがちですが、「寒暖差アレルギー」も疑ってみてください。
その名の通り「寒暖差アレルギー」は、寒暖差によって自律神経が乱れることで起こります。血管は寒いと縮み、暑いと広がります。寒暖差が激しいと、血管の収縮が環境に追いつかなくなり、自律神経が誤作動を起こし、体に不調をもたらしてしまうそうです。自律神経は激しい気温差で乱れるのが特徴で、特に7度以上の気温差がある場合、症状が起きやすいといわれています。
アレルギーや風邪との違い
一般的にアレルギーには、花粉・食べ物・金属といった原因となるアレルゲンがありますが、「寒暖差アレルギー」にはアレルゲンはありません。
また、風邪のような感染症は、鼻水から始まってのどの痛みや発熱など、免疫による防衛反応が起こりますが、「寒暖差アレルギー」では、熱が出ることはまれで、鼻水は水のようにサラサラしているのが特徴です。
つまり、身体が激しい温度差に耐え切れなくなった時に、寒暖差アレルギーは起こります。ここで耐え切れないという場合、およそ7度を超えると起こりやすいといわれる外部の温度差の要因もありますが、一方、仕事で疲れているとか、ストレスが高じているといった、免疫が低下したり、自律神経が乱れているといった、ヒトの側の要因も発症に関連してきます。
「寒暖差アレルギー」になったら
症状によって診療科も変わってきますが、おもな症状の鼻水・鼻づまり・クシャミなどで受診するなら、耳鼻咽喉科での治療が必要になります。また、免疫の低下や自律神経の乱れが酷いなら、内科や心療内科も考えられます。
もしジンマシンが出ているようなら皮膚科、睡眠障害がつらければ精神科や睡眠外来などの受診も必要になるでしょう。たとえば、耳鼻咽喉科の場合、症状の鼻づまりなどへの対処として、点鼻薬などを処方してくれる場合もあります。念のため血液検査やレントゲンで、免疫や自律神経の状態を調べることもあるそうです。
関連するまとめ
 大河原奈々未
大河原奈々未
地元横浜のスポーツチームをこよなく愛しています。
マリノスもベイスターズもビーコルも、頑張れ~
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
アンケート特集
みんなはどう思っている?

運動の時の水分補給!!気になるスポーツドリンクの成分とは?
スポラボ編集部 / 888 view

数あるスポーツドリンク!よく飲まれているのは?
スポラボ編集部 / 857 view

やっぱりスポーツのできる男はかっこいい?
スポラボ編集部 / 1128 view