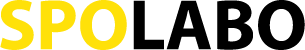ビールの定義とは?
ビールといえば、「麦を原料として炭酸入りの低アルコール飲料」というのが一般的なイメージかと思います。
はじめに
日本で1番飲まれているお酒といえばビールではないでしょうか?
とりあえず乾杯はビールでという程ですね。
そんな人気なビールですが、どんな定義なのでしょうか?
今回はそんなビールの定義について紹介します。
定義
ビールといえば、「麦を原料として炭酸入りの低アルコール飲料」というのが一般的なイメージかと思います。
もう少し踏み入れると「麦芽(モルト)とホップを使用した低アルコール飲料」に当てはまるお酒が一般的にはビールと呼ばれています。
では「ビールの定義」はどうなっているのでしょうか?
ビールの定義は各国異なり、日本の場合、酒税法にてビールは定義付けされています。
■酒税法上のビールの定義
次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又はカラメルを原料として発酵させたもの(その原料中米以下の物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る。)
(酒税法第3条第12号)
※麦芽重量の半分以上のその他原料を使用したり、使用が認められない原料を使用すると「発泡酒」に分類されます。
ちなみに日本の酒税法では、アルコール度数が1度以上のものをお酒とみなします。
つまり日本におけるビールは「アルコール1度〜20度」ということです。
発泡酒の定義
◆「発泡酒」の定義
ビールと同じ原材料を発酵させたもので、
・麦芽比率50%未満のもの
・麦芽比率50%以上であっても、
ビールに使える原料以外の原料を使用したもの
・麦芽比率50%以上であっても、
規定量を超えて副原料を使用したもの
これらが「発泡酒」です。但し、蒸留酒等を原料に含むものを除きます。
関連するまとめ

あなたは今までにいくつ巡ったことがありますか?困った時や頼りにしたい時のパワースポッ…
今巷で流行っているパワースポット巡り。ただあまり場所にも詳しくないそんなあなたは必見です。関東のパワースポッ…

住宅ローン擬人化 連続10秒ドラマ『運命の借換』が累計再生回数900万回
auじぶん銀行株式会社が2021年1月13日に公開した動画「auじぶん銀行 住宅ローン 連続10秒ドラマ『運…
 岩永美月
岩永美月
ソフトボールをずっとやってきたので野球大好きです。
12球団のホーム球場制覇まで、残すは日ハムのみ。
日ハムの新球場完成したら観戦しに行って、12球団のホーム球場制覇してみせます!
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

すばやく疲労回復させる大豆ペプチド
スポラボ編集部 / 895 view

スポーツドリンクの成分について
スポラボ編集部 / 803 view

アイソトニックとハイポトニックについて
スポラボ編集部 / 9875 view