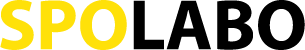かぼちゃは炭水化物、β-カロテン、ビタミンC、食物繊維を含み、うり科の中ではいちばん高エネルギーの栄養食品です。
江戸時代より「冬至にはかぼちゃ」というほど栄養満点のかぼちゃは、大切な冬の定番野菜。
かぼちゃとは
かぼちゃの名の由来は、ポルトガル人が寄港地のカンボジアからもたらしたことにちなむといわれています。かぼちゃは、大きく分けて「日本かぼちゃ」「西洋かぼちゃ」「ペポかぼちゃ」の3種類があります。一番最初に日本に伝来したのは「日本かぼちゃ」。味は淡泊ですが、粘りがあり、煮くずれしにくいので、煮物や蒸しものに向いています。現在では糖質の多い「西洋かぼちゃ」が日本のかぼちゃの大半を占めています。
歴史とは
日本かぼちゃ」は16世紀中頃(1541~1550年)にカンボジアに寄港したポルトガル船によって豊後(大分県)にもたらされました。その際「カンボジア」がなまって「かぼちゃ」という名前になったといわれています。なお日本かぼちゃの原産地は中央アメリカから南アメリカ北部の熱帯地方とされています。
現在、主流となっている「西洋かぼちゃ」は、原産地が中央アメリカから南アメリカの高原地帯で、日本へは19世紀中頃にアメリカから伝わったといわれています。栽培が本格的に始まったのは明治時代になってからで、東北や北海道などで生産が増えていきました。
「ペポかぼちゃ」は北アメリカ南部が原産地で、西洋かぼちゃより少し遅れて日本に入ってきました。
栄養とは
かぼちゃには、ビタミンAの元となるβカロテンやビタミンB群、ビタミンEのほか、カルシウムなどがバランスよく含まれています。
その中でも特に多い栄養素がβカロテン。βカロテンには免疫力を高める効果があり、1年の中で最も昼の時間が短い冬至(とうじ、今年は12月22日)に、日本では寒さに備えてかぼちゃを食べる習慣があります。かぼちゃに含まれる体を温める効果、ビタミンA、Cには細菌やウイルスを撃退する効果があるので、空気が乾燥し寒さで体調を崩しやすい冬にぴったりな食べ物なのです。さらにビタミンAには、脳卒中やガンなどの原因である活性酸素を除去する働きも。 このように、たくさんの栄養素を含むかぼちゃは様々な病気の予防としても大活躍する野菜です。
かぼちゃの皮や種、わたを捨てていませんか?実はこれらにもたくさんの栄養が含まれているのです。まず、かぼちゃの皮にはβカロテンがたっぷり。かぼちゃ料理をつくる時は、ぜひ皮も一緒に食べてください。種には、ミネラルや鉄分などのほか、悪玉コレステロールの値を下げてくれるという「フィトステロール」、コレステロール値の上昇を抑えてくれるという「不飽和脂肪酸」が多く含まれています。わたには食物繊維がたっぷりで、なんとβカロテンも果肉の約5倍。かぼちゃは丸ごと栄養満点の野菜なのです。
関連するまとめ

春の山菜のひとつのわらび。お浸しにしても美味しいですよね。そんなわらびの効果は?
春から初夏にかけてが美味しくなる山菜のひとつです。 日本で自生する場所は、日当たりのよい山地や草原で、ぜんま…

お正月のおせち料理に、縁起物として食べることの多い黒豆。どんな効果があるのでしょうか…
一般的に、大豆類に属する黒大豆のことを“黒豆”と呼んでいます。 黒豆の黒い色には邪気を払う意味があり、さらに…
 takuji
takuji
こんにちわ。
クエン酸と、テニス大好き少年です。プレーするのも、観戦するのも大好きです。
得意なのはフォアストロークです。アプローチから相手を追い込み、ボレーで決めるのが
基本的なスタイルです。苦手なのはバックです。弱点を隠し、なるべくフォアに回り込んで打つ癖で、弱点が余計に目立つようになりました。
これからも、弱点から逃げずにバックを克服していきます。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
アンケート特集
みんなはどう思っている?

手軽に水分補給!!どんな時にスポーツドリンクを飲む?
スポラボ編集部 / 895 view

顔だけじゃない…理想のカラダの男性有名人といえば?
スポラボ編集部 / 832 view

メタボ対策!?運動する頻度は?
スポラボ編集部 / 873 view