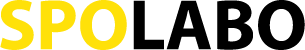10月に行われるお祭りを紹介します。ぜひ見たことがない人はご覧あれ。その14
漁師町の舞阪で豊漁を祈願して行われる岐佐(きさ)神社の祭典。遠州の奇祭として400年以上の歴史があります。
舞阪大太鼓まつり
漁師町の舞阪で豊漁を祈願して行われる岐佐(きさ)神社の祭典。遠州の奇祭として400年以上の歴史があります。旧暦の9月14日、15日の二日間にわたって、宵祭、本祭りと行われます。
本祭りの朝、太鼓が神社境内で一斉に鳴り響きます。大太鼓は大きなもので直径約2.5メートルあり、バットのようなバチで豪快に打ち鳴らされます。全身を使って叩くその姿は一見の価値あり。放たれる音、振動は体にビリビリと伝わってくる大迫力です。
昼間は、神輿の渡御にともなって行列を組み、手踊りの屋台も加わって町内を練り歩きます。夜になると行列は神社に戻り、拝殿前の石段を大太鼓が昇って最高潮の盛り上がりを見せます。
見所
大太鼓は明治中頃は直径2尺(約61cm)、大正時代には4尺(約121cm)ほどのものでしたが、昭和5年に直径6尺弱(約180cm)の大太鼓が使われ、それをきっかけに各町で、次第に太鼓の大きさを競いようになり、昭和9年には直径6尺(約182cm)、昭和12年には7尺2寸(約218cm)という、当時では類をみないほどの大きさの太鼓が作られました。
現在、直径7尺8寸(約236cm)の太鼓が最大。大きさに比例して音は、地の底から響くような迫力があり、祭礼の代名詞にもなっています。
太鼓を叩くバチ(撥)も巨大で、約1m。男たちは連日、拳に巻きつけた晒(さらし)に血が滲むまで力の限り叩き続けます。
「革の張り替えには100万円近い費用がかかるため、簡単に張り替えることができず、祭りを仕切る年番が回ってきた年に新調する町内が多い」(舞阪大太鼓保存会)とのこと。
旧暦9月15日は大安吉日のハレの日にあたり、月明かりに照らされた大太鼓一行は幻想的ですらあります。
関連するまとめ

エナジードリンク美味しいし元気にもなるけど、飲みすぎにも注意は必要!?
清涼飲料水と比べると、カフェインの含有量が多く、強炭酸で強い甘みがあるのがほとんどのエナジードリンクの特徴で…
 takuji
takuji
こんにちわ。
クエン酸と、テニス大好き少年です。プレーするのも、観戦するのも大好きです。
得意なのはフォアストロークです。アプローチから相手を追い込み、ボレーで決めるのが
基本的なスタイルです。苦手なのはバックです。弱点を隠し、なるべくフォアに回り込んで打つ癖で、弱点が余計に目立つようになりました。
これからも、弱点から逃げずにバックを克服していきます。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

アイソトニックとハイポトニックについて
スポラボ編集部 / 9872 view

スポーツドリンク比較-Part1
スポラボ編集部 / 978 view

スポーツドリンクを購入!!選ぶポイントって何?
スポラボ編集部 / 911 view