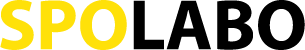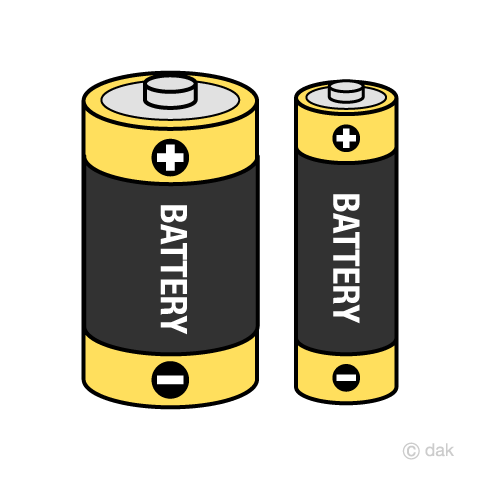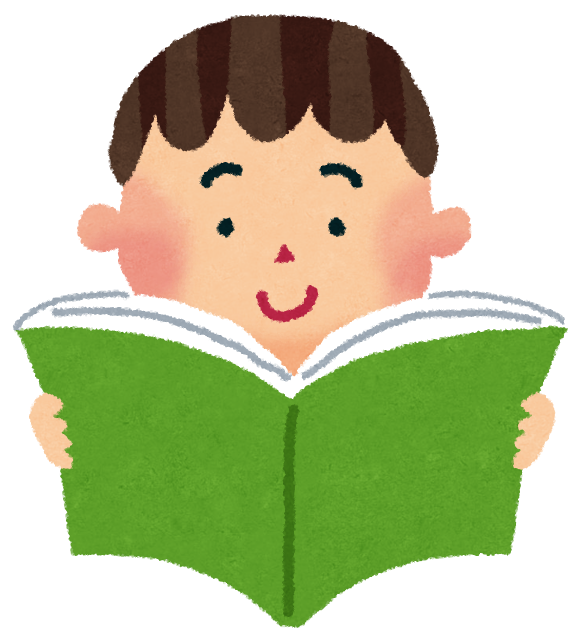あなたが信じていたその常識は実は間違いだった!?こんなにもあった間違い常識 パート②
今まで信じてきた常識が実は間違っていたという事ってありませんか?その代表的な間違いをまとめてみましたので、ご紹介します。
「電池は使い切ってから充電」したほうがいい。は昔の話。
「電池は使い切ってから充電」というのは、実は過去の話。以前携帯電話に使われていた「ニッケル水素電池」や「ニカド電池」といった電池では、継ぎ足し充電を繰り返すことで電池自体の容量が減ってしまう「メモリー効果」という現象が見られましたが、現在主に使われている「リチウムイオン電池」の場合は、そのような心配はないそうです。
携帯電話の電波がペースメーカーを誤動作させることがあるのは昔の携帯の話。
近年流通しているほとんどの携帯電話(第3世代以降)では、最悪条件時でも3cm以内に密着させない限り影響はありません。
●携帯電話の電波は心臓ペースメーカーを誤動作させる可能性がある
●ただし、その「可能性」は
・ 旧型の携帯電話(出力が強い)と、もっとも誤動作しやすいペースメーカーの組み合わせ
・ かつ、送信出力やペースメーカーの感度を最大にするなど最も悪条件の場合
・ かつ、15cm以内に近づいた時のことである
薄暗いところでの読書は目が悪くなる?そんなことはない。
暗いところで読書をすることが目に負担をかけるのは事実ですが、それが視力の低下につながるという医学的根拠はありません。
お酢を飲むと体が柔らかくなる?なりません。
料理をするときに肉をお酢につけておくと、酵素の働きによってタンパク質が分解されて柔らかくなるという効果があります。このことから「お酢=肉を柔らかくする=人体も柔らかくなる」という発想が生まれたのかも知れません。が、お酢の成分は消化の過程で分解されてしまうので、もちろん柔らかくなりません。
耳に唾をつけると水が入らない?いいえ、入ります。
耳にツバをつけたところで、水をはじいたり、水が入るのを防ぐ効果はありません。
この間違った知識は、昔の漁師がしていたことが誤って広まったためだそうです。
昔、素潜りの漁の漁師は、やわらかい草をまるめて耳に詰め、それを耳栓がわりにしていました。ツバをつけて草を丸めやすくしておいてから、耳に詰めていました。
ところが、その様子を見た人のなかに、草を丸める動作を飛ばして、ツバをつけた指を耳の中に入れるという動作だけを真似た人がいたのでしょう。そこから「耳にツバをつける」という誤った動作が定着したらしいです。
関連するまとめ

あなたが信じていたその常識は実は間違いだった!?こんなにもあった間違い常識 パート④
今まで信じてきた常識が実は間違っていたという事ってありませんか?その代表的な間違いをまとめてみましたので、ご…
 Yuta
Yuta
筋トレ、走ること、食べることが好きです。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

水とスポーツドリンクどっちを飲むのがよいのか?
スポラボ編集部 / 829 view

スポーツドリンクを購入!!選ぶポイントって何?
スポラボ編集部 / 918 view

運動時にスポーツドリンクの効果的な摂り方
スポラボ編集部 / 772 view