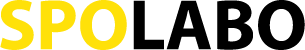秋刀魚の力
秋の味覚のさんまですが、いつ食べても美味しいですよね。
塩焼き、刺身。
どれも好きです。
疲労回復
タンパク質は脂質炭水化物とともに“三大栄養素”とされており、エネルギー源として働く他、内蔵・筋肉・皮膚などをはじめ体を構成する様々な細胞の主成分となる成分です。大きく分けて肉・魚・卵などの動物性蛋白質と、豆・ナッツなどに含まれている植物性タンパク質がありますが、概ね動物性タンパク質のほうがアミノ酸のバランスが良いとされています。サンマもアミノ酸スコアが100(最高値)ですから良質なタンパク源と言えますし、タンパク質の代謝・合成に関わるビタミンB6やB12も豊富に含まれています。アミノ酸のBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)は筋肉疲労の予防・回復促進に有効とされていますし、体力や筋肉の向上にも欠かせない存在です。
骨粗鬆症予防
さんまにたっぷり含まれている栄養ビタミンD。実は、骨粗しょう症予防に効果的な栄養素です。ビタミンDには、カルシウムの吸収を促進させる効能があります。歯や骨を構成するカルシウムの濃度を高め、強くて太い骨の形成をサポートします。さんまにはビタミンDもカルシウムの栄養も含まれているので、骨太な肉体を作るのには最適な食材です。とくに、骨粗しょう症のリスクが高まる高齢の方におすすめしたい食材です。ちなみに、より多くのカルシウムを摂取したいときは、さんまの缶詰もおすすめです。缶詰は骨まで丸ごと食べられるため、カルシウム含有量は焼いたさんまの6~7倍近くになります。
貧血予防
さんまに含まれているビタミンB12も、EPAと同じく血液の改善に効果を発揮する栄養です。ビタミンB12には、骨髄の造血機能を活性化させて、赤血球の生産量を増やす効果があります。これによってカラダの末端まで酸素が行き渡るように血液の状態を改善し、悪性貧血の予防につながります。貧血でお悩みの方には、ビタミンB12を豊富に含んでいるさんまがおすすめです。熱にも比較的強いので、塩焼きや煮付けにしても無駄なく摂取できます。また、ビタミンB12には神経機能を正常に保つ働きもあります。そのため、ビタミンB12が不足すると、手足のしびれや集中力の低下、気分が塞ぎやすくなるなどの症状がでます。
さんまと大根おろしの関係
塩焼きにしたさんまには、必ずといっていいほど大根おろしがついてきます。ジューシーなさんまと、後味をすっきりとさせてくれる大根おろしはまさにゴールデンコンビ。実はその組み合わせには味や栄養の相性だけではない、深いワケがあったのです。さんまを塩焼きにするとき、どうしても気になってしまうのが焦げ。焦げには発ガン性物質が含まれており、そのまま食べるのは抵抗感があるという方も多いはず。そこで、大活躍するのが大根に含まれるイソチオシアネートという辛味成分。実はこのイソチオシアネートには抗酸化作用があり、これが発ガン性物質からカラダを守ってくれる効果があります。
関連するまとめ

そろそろハロウィンの季節ですね!ハロウィンのシンボル「かぼちゃ」の栄養とは
いまや国民的な行事となったハロウィン。今年はコロナの関係で、どうなるんでしょうか?ところでハロウィンといえば…
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
アンケート特集
みんなはどう思っている?

数あるスポーツドリンク!よく飲まれているのは?
スポラボ編集部 / 862 view

顔だけじゃない…理想のカラダの男性有名人といえば?
スポラボ編集部 / 830 view

スポーツする時の大切な水分補給!!何を飲んでる?
スポラボ編集部 / 833 view