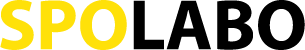怪我した部位や目的に応じて効果の変わるテーピング
テーピングとは
テーピングはスポーツ選手がケガをした時にするイメージが大きいと思います。しかし、テーピングにはいろいろな種類があり、その効果や意味はさまざまです。
スポーツだけではなく高齢者や一般の方も、意味のある貼り方次第ではいろいろ効果が期待でき、応用できます。
ケガの予防はもちろん、痛みの抑制や姿勢改善にも意味があり、効果を発揮します。
ここではそんなテーピングにはどんな効果があるのか、どういった意味があるの、どう使い分けたら良いのかを説明してきたいとおもいます。
テーピングの効果
テーピングの1番の効果としては、ケガをした際の固定をすることで、つまりは「痛みの抑制」の意味があります。
テーピングの起源は諸説ありますが、約150年程前に戦争中にケガをした兵士がテープをぐるぐる巻きにした事が始りとされています。それがスポーツの分野で発展し現在に至ります。
現在ではスポーツのケガだけではなく、ケガの予防や日常生活でも姿勢の矯正などにも効果があり、意味のあるテーピングの使い分けが出来るようになりました。
テーピングの意味
テーピングの意味とは、スポーツでのケガの固定だけではなく、ケガ予防や身体機能の向上を目的とした貼り方や姿勢の矯正にも使える意味があり使い分ける事ができます。
現在ではテーピングの種類もたくさん増え、そのカラーもさまざまです。
それぞれに意味があり、
それらを使って身体機能の向上だけではなく、精神的な面でも安定させて気持ちを高揚させる意味もあります。
スポーツをしていない一般の方でもケガをしてしまった人、ケガをしたくない人、またはケガをしてしまったがそれでも続けたい人、以前にケガをした部位の予防などに対して、ファッション面をも考慮したテーピングができる意味もあり、使い分ける事ができます。
ケガをした部位、目的に応じて使い分ける事で効果が違う
どのスポーツでもケガが多いのかは、競技によって様々ですが大きく使い分けると、
可動性が大きな関節に効果や意味を発揮します。
例えば、肩関節・肘関節・膝関節・足関節といったのが代表的なのになります。
ケガをして応急処置目的で固定する場合は、非伸縮性のテーピングで関節が動かないように固定するのが効果的です。痛みがあるが競技を続けなければいけない、動かなければいけないという時にも、非伸縮性のテーピングで関節可動域を制限する事で効果や意味があります。
ケガの予防や身体機能の向上を目的にテーピングを行う場合は、伸縮性のテーピングをつかって筋肉をサポートし、疲労軽減等にも効果と意味を発揮します。
関連するまとめ
 大河原奈々未
大河原奈々未
地元横浜のスポーツチームをこよなく愛しています。
マリノスもベイスターズもビーコルも、頑張れ~
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

スポーツドリンクの成分について
スポラボ編集部 / 809 view

スポーツドリンク比較-Part2
スポラボ編集部 / 842 view

運動の時の水分補給!!気になるスポーツドリンクの成分とは?
スポラボ編集部 / 894 view