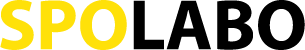牡蠣の栄養と効果をご存じですか?
今が旬の牡蠣について纏めました。栄養と効果や、あたると言われている原因についてです。
牡蠣の特徴
①貝柱は一つ
二枚貝でもアサリやハマグリなどは貝柱が2個あるのに対し、牡蠣には一つしかありません。殻を開ける時はナイフを差し込み、真ん中あたりにある貝柱を殻から切り離します。
②内臓が大きい
牡蠣は一旦岩場などに着くとずっとそこに固着し、潮の流れによって餌を取り込むので移動するための筋肉が発達せず、大部分が内臓となるそうです。
流通しているものは養殖がほとんどです。岩牡蠣は天然物で漁獲量が限られており、流通量が少なく、期間も短いため、希少価値が高いです。
概ね、岩牡蠣はほとんどが天然物で主に日本海側で獲れ、真牡蠣は養殖物がほとんどで主に太平洋側で養殖されています。
牡蠣の栄養と効果
①亜鉛
牡蠣は亜鉛を多く含んでいるのが特徴で、味覚障害の予防に必須の成分です。そのほかにも、多くの酵素やインスリンの構成成分となっています。
②貧血予防
鉄や銅などのミネラルを多く含み、貧血予防に効果があります。特に牡蠣に含まれる鉄分はヘム鉄と呼ばれる体内に吸収されやすい形なので効率よく摂取することができます。
③タウリン
タウリンを非常に多く含んでいます。乳酸の増加を防ぎ、スタミナ増強、疲労回復に効果があります。また、胆汁酸の分泌を促し、コレステロールの上昇を抑える作用や、眼の疲れや、視力の衰えを回復する効果もあるそうです。
牡蠣の保存方法
牡蠣はアサリやハマグリとは違い、海水に浸しておかなくても1週間くらいは生きています。これは干潮時に干上がる岩場などでも生きていられる性質によるものです。ただ、直接氷に長時間当てて冷やすと死んでしまうようなので注意が必要のよです。
牡蠣には「生食用」と表記されているものと、「加熱用」とされているものがあります。生食用とはウイルスや菌がいない海域で育てられたものか、水揚げされてから一定の時間紫外線などで滅菌された海水で清浄されたりしたもので、様々な条件をクリアし、生のまま食べても食中毒を起こす原因菌がほとんど含まれていないものです。生食用とされているものの中には、滅菌処理などの過程で身痩せしたり、旨みも流失していまうケースもあるようなので、加熱して食べるのであれば加熱用の牡蠣がおすすめのようです。
余談ですが、牡蠣を食べるとあたるということを耳にしますが、牡蠣にあたるといっても、その原因はさまざま。なかでも主な原因となるのが、以下の通りです。
1. ノロウイルス
2. 腸炎ビブリオ
3. 貝毒
4. アレルギー
牡蠣にあたる人のなかでもっとも多いのが、ノロウイルス。また、牡蠣を食べると毎回あたるという人は、アレルギーの可能性を疑う必要があるそうです。
関連するまとめ
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

スポーツドリンク比較-Part2
スポラボ編集部 / 837 view

運動時にスポーツドリンクの効果的な摂り方
スポラボ編集部 / 763 view

運動の時の水分補給!!気になるスポーツドリンクの成分とは?
スポラボ編集部 / 888 view