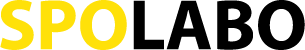ビタミンK
ビタミンの種類・効果を知ろう第5弾
皆さん、「ビタミンK」ってどんなビタミンかご存知でしょうか?
あまりピンとこない方もいるかもしれませんね。
今回は、ビタミンKについて見ていきましょう。
ビタミンKの効果
血液を固める作用
怪我したときの大量出血や内臓での出血が起きた時に、血液が固まるためには「凝固因子」と呼ばれる物質が必要になります。
その凝固因子の中には、作る過程でビタミンKが必要なものがあります。
ビタミンKが不足すると凝固因子の生成が少なくなり、血液の凝固作用が低下してしまいます。
その結果、血が固まりにくくなります。
腸内でもビタミンKは生産されるため不足することはありませんが、薬などの影響で腸内環境が変化して腸内細菌が減ってしまうと、ビタミンKの生産が減少してしまいます。
骨の形成
骨は、骨吸収(古くなった骨の破壊)と骨形成を絶えず行っています。
加齢による骨量減少作用は、骨吸収と骨形成のバランスが崩れ、骨吸収が骨形成に勝るために起こります。
ビタミンKは、新しい骨を作ったり、骨にカルシウムをためたりする際に必要なタンパク質「オステオカルシン」を介して骨形成の促進に働きます。
また、ビタミンKは骨吸収の抑制にも作用します。
そうすることで、より骨の形成を促進することができるのです。
ビタミンKを多く含む食材
納豆(含有量 600μg/100g)
ビタミンKの含有量100g当たり600μgと、納豆にはビタミンKが多いです。
納豆菌により生成されるビタミンK以外にも、腸内でビタミンKが作られるのを納豆菌が助けるため、それ以上のビタミンKを摂ることができます。
納豆消費量が多い県では、骨折頻度がとても低い傾向があるといわれるほどです。
1日1パック食べることで、十分に必要量を満たすことができます。
パセリ(含有量 850μg/100g)
パセリは、付けあわせとして出てくることが多い野菜ですが、ビタミンKを多く含んでいる食品の1つです。
小さなパセリの葉を4本食べるだけで、必要量を十分に満たすことができます。
何かの料理に混ぜていただくとよいでしょう。
しその葉(含有量 690μg/100g)
薬味として食べられることが多いしその葉。
一度にたくさん食べるものでもありませんので、てんぷらや紫蘇ジュースとしていただくのもよいでしょう。
葉物野菜(含有量 300μg以上/100g)
春菊・モロヘイヤ・ほうれん草・にら・小松菜だけでなく、かぶの葉・大根の葉の部分にも多く含まれています。
春菊ビタミンKの含有量100g当たり460μg、モロヘイヤビタミンKの含有量100g当たり450μg、かぶの葉ビタミンKの含有量100g当たり340μgのように、ほとんどの葉物野菜が100g当たり300μg以上ビタミンK含みます。
グリーンスムージーにしていただいたり、野菜炒め、みそ汁に葉物野菜を使ってみてもよいでしょう。
おわりに
腸内細菌がビタミンKを作ってくれていたなんて驚きですよね。
そのため余程のことがない限りは、ビタミンKが足りなくなることはありません。
ですが、抗生物質の投与により腸内細菌叢に大きな変化が起こり、腸内細菌によるビタミンKの合成が低下し、ビタミンK欠乏状態に陥ることがあります。
食事からも摂取するようにしましょう。
関連するまとめ

ウォーキングするなら朝がいいらしいですよ!で、どんな効果があるのでしょうか。
最近、ダイエットや運動不足解消にウォーキングを始める人が、 増えていますね。 朝の早い時間や、仕事の後の時間…
 中山葵
中山葵
スポーツ全般大好きです。
球技は特に大好きで、バスケをよく観戦しています。
今までスポーツは観る専門でしたが、これからは色んなスポーツをやっていきたいと思っています。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

手軽に水分補給!!どんな時にスポーツドリンクを飲む?
スポラボ編集部 / 885 view

スポーツドリンクを購入!!選ぶポイントって何?
スポラボ編集部 / 911 view

水とスポーツドリンクどっちを飲むのがよいのか?
スポラボ編集部 / 821 view