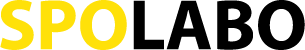テニスのハードコートとは
テニスコートにはいくつかの種類がありますが、世界のツアーで最も多く使われているハードコートの特徴について、ご紹介いたします。
テニスのハードコートとは
テニスコートにはいくつかの種類がありますが、世界のツアーで最も多く使われているハードコートの特徴について、その構造や表面素材、プレーする上でのポイントについてまとめてみました。ここではハードコートを「表面素材が合成樹脂であるコート」と定義してご説明します。
ハードコートとは、表面が硬い(ハード)コートの事をハードコートと呼びます。
四大大会と呼ばれる 全豪、全仏、全英、 全米のオープン大会のうち、 全豪と 全米で使われており、日本では、デビスカップやフェドカップなどの国別対抗戦が行われる東京・ 有明テニスの森コートや大阪・靭テニスセンターなどはハードコートの代表です。
ハードコートは不規則なイレギュラーバウンドはほとんどないのですが、一般的にボールがバウンドしてから速く高く跳ね、特にルール上は表面素材の禁止規定はないので、表面の合成樹脂次第でバウンドが異なるコートです。
ハードコートの構造と表面素材
ハードコートは、ベースをセメントやアスファルトで固め、表面に合成樹脂を塗ることが基本的な施工方法になります。
最近では表面の下にクッション性のある素材を敷く施工もあります。クッション性の強弱や、表面の合成樹脂の性質が、バウンドしたボールの速さや高さ、プレーする選手の疲労度に影響を与えます。
表面素材の合成樹脂には、エマルジョン系のアスファルト・アクリル・シリカ・EVA、ポリウレタン系、ゴムチップウレタン系、ポリエチレン系などの化学素材で、それぞれの弾力や耐久性で特徴があります。表面が土のクレーコートや人工芝のオムニコートと違い、地表に砂は撒かないコートです。
ハードコートの特徴
世界のツアーでは最も多く使われている
海外のツアーを視野に入れている日本のトップクラスの選手やジュニア選手育成の場では、海外のツアーで最も多く使われているコートです。
そのため、ハードコートが見直されてきており、特に将来性のあるジュニア選手の指導者たちは、日本のジュニア選手たちには、若いうちから世界で主流のハードコートでスピーディーなテニスに慣れさせるべきだと主張しているほどです。やはり、世界に目を向けるのであれば、世界で最も使われているハードコートで練習できる環境を増やす事が、日本でも必要なのかもしれません。
雨に強く維持管理がしやすい
テニスコートの種類の中では、雨に強いタイプで、雨が止んだ後に生じる水溜りをワイパーで掃けば比較的早くプレーを再開できます。しかし雨が止んだらすぐにもプレーを再開できるオムニコートが紹介され、普及してからは少数派となりつつあります。
また、雨の降り始めは一番滑りやすく、足首のねんざなどのけがが多いので注意が必要です。
またハードコートは、クレーコートより初期投資費用がかかりますが、メンテナンスについては数年おきに表面の合成樹脂の塗り直しだけで済むため、維持管理が楽で費用も多くはかからないことから、日本でもオムニコートが本格的に導入されるまでは、一時期盛んに施工されました。
バウンドしてからのボールが速く、跳ねる
ボールがバウンドしてからの速度は、他の表面素材のコートと違い速く、バウンドしてからボールが伸びまるという特徴を持ちます。
サーブやストロークの威力で相手を圧倒することができ、スピード重視の攻撃的なテニスを得意とする選手には最も良いコートと言えます。また、普段からボールの速さに慣れていないと、慣れるまでに少し時間がかかるコートです。
また、ボールのバウンドは高く跳ねるため、ストロークでは上からかぶせるようなスピン系のショットや、威力のあるサーブ、そしてコートにたたきつけるようなスマッシュでポイントを取りやすく、攻撃的なショットが効果的なコートです。
足腰に負担がかかりやすい
ハードコートは、化学素材の合成樹脂の下の土台がセメントやコンクリートだけに、足腰への負担はどうしても大きくなります。
また、クレーコートと違い表面に砂が撒かれないため、コート表面と シューズの底との間に遊びが少ないため滑りにくく、コートに シューズが引っかかりやすく、足首のねんざ等けがも多いコートです。ボールは素直なのですが、初心者が学ぶ入門用のコートとしては難しいかもしれません。
関連するまとめ

世界女王、大坂なおみ選手が大好きな『抹茶アイス』をワンコインで提供!「ロールアイスク…
ロールアイス専門店「ROLL ICE CREAM FACTORY」は、テニスの全豪オープン女子シングルで優勝…
 大河原奈々未
大河原奈々未
地元横浜のスポーツチームをこよなく愛しています。
マリノスもベイスターズもビーコルも、頑張れ~
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

スポーツドリンクを購入!!選ぶポイントって何?
スポラボ編集部 / 911 view

自家製スポーツドリンクの作り方
スポラボ編集部 / 773 view

スポーツドリンク比較-Part1
スポラボ編集部 / 978 view