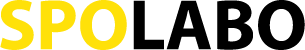勤労感謝の日って?
年内最後の祝日である「勤労感謝の日」ですが、意味や由来などを説明できますか?
今回は「勤労感謝の日」について調べてみました。
勤労感謝の日の意味
年内最後の祝日である「勤労感謝の日」ですが、祝日法という日本の法律で、「勤労を尊び、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」という意味があります。
簡単にいうと、「仕事を大切にし、働くことによって得られた成果を喜び、国民がお互いに労いと礼の気持ちを持つ」ということです。
勤労感謝の日の由来は?
勤労感謝の日の起源は、五穀豊穣を祝う「新嘗祭」が起源とされています。
新嘗祭が勤労感謝の日になった理由は、戦後、「天皇の宮中行事と国民行事を切り離す」というGHQの考えにより、1948年(昭和23年)から国民の祝日である「勤労感謝の日」へと変わったと言われています。
新嘗祭が起源ということで、勤労感謝の日は働く人に感謝をすることと同時に、仕事の成果=農作物の恵みに感謝する日でもあります。
起源となった新嘗祭とは?
新嘗祭とは、日本書紀にも記されているほど、古くから伝わる伝統行事で、農作物の恵みに感謝する宮中行事です。
天皇が国家と国民の安寧と繁栄のため、神に祈願することを目的とした「宮中祭祀(きゅうちゅうさいし)」のひとつです。
読み方ですが、「にいなめさい」または「しんじょうさい」と読みます。
新たに収穫した五穀を天と地の神々に供え、天皇自らも新穀を食べることにより、その年の収穫に感謝することから、現代でいうところの収穫祭にあたる祭りともいえるのではないでしょうか。
勤労感謝の日をただの祝日とするわけではなく、しっかりと由来を知った上で過ごすと過ごし方が少し変わるかもしれませんね。
関連するまとめ

青森が全国に誇る夏の一大イベント「青森ねぶた祭り」。由来や掛け声の意味を紹介します。
東北の夏を代表する祭りのひとつ、青森ねぶたは昭和55(1980)年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

スポーツドリンク比較-Part2
スポラボ編集部 / 838 view

手軽に水分補給!!どんな時にスポーツドリンクを飲む?
スポラボ編集部 / 890 view

すばやく疲労回復させる大豆ペプチド
スポラボ編集部 / 895 view