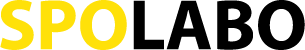日本文化の1つ捕鯨の歴史
縄文時代の前期までは、沿岸に流れ着いた寄り鯨を海からの恵みとして利用していたと考えられています
はじめに
みなさんはクジラ肉を食べた事はあるでしょうか?
昔は給食にもクジラの竜田揚げなどが出た時代もあったとか。最近になって日本は、クジラ漁の国際的な取り決めをつくる国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退し、IWCの規制を守る必要がなくなりましたね。
IWC加盟国は、捕鯨を実質的に禁止することで合意しています。これに対し日本は、持続可能な方法でクジラを捕ることはできると長年、主張してきましたね。
捕鯨の歴史
縄文時代の前期までは、沿岸に流れ着いた寄り鯨を海からの恵みとして利用していたと考えられています。その後、縄文時代の中期になると積極的に海に出て捕獲を行うようになったと考えられます。捕獲した鯨は食用として利用されたほか、不可食部位の骨なども土器の製造台などとして有効利用していたことが分かっています。
江戸時代の初期になると鯨組による組織的な捕鯨が始まり、その後網掛け突き取り式捕鯨と呼ばれる効率的な漁法が開発されると鯨の供給量は大幅に増加します。
当時は生肉類の保存技術がなかったため、赤肉や皮類は塩蔵して全国の消費地へと出荷され、内臓類等は主に産地で消費されていました。
敗戦後の食料に
敗戦後の食糧難の時代、日本人を栄養面から救ったのも鯨でした。鯨肉は栄養価の高い安価な食材として庶民の食生活を支え、学校給食でも子どもたちの健康を育む重要なメニューとして供されてきました。
1962年までは国民一人当たりの食肉供給量で鯨が牛、豚、鶏を上回っていたことからもその恩恵がうかがえます。
最後に
日本がIWCを脱退した事で、諸外国から批判などもありましたが、今後の日本の商業捕鯨がどのように行われるのか、注目していきたいですね。
関連するまとめ
 岩永美月
岩永美月
ソフトボールをずっとやってきたので野球大好きです。
12球団のホーム球場制覇まで、残すは日ハムのみ。
日ハムの新球場完成したら観戦しに行って、12球団のホーム球場制覇してみせます!
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
アンケート特集
みんなはどう思っている?

スポーツする時の大切な水分補給!!何を飲んでる?
スポラボ編集部 / 797 view

水分やミネラルなどを補給できるスポーツドリンク!飲む頻度は?
スポラボ編集部 / 804 view

数あるスポーツドリンク!よく飲まれているのは?
スポラボ編集部 / 821 view