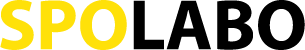アルコールが好きなら肝臓をいたわろう
アルコールは「百薬の長」とも言われ、適量なら健康に良いという一面を持っているのですが、大量に摂取すると肝臓をはじめ膵臓やその他体中の多くの臓器に悪影響を及ぼしてしまいます。
肝機能異常とは
「肝機能異常」とは、一般的にAST(GOT)、ALT(GPT)が基準値を上回っている状態であることをいいます。AST、ALTは、健康診断や人間ドックから医療機関における詳しい検査まで、広く行われている検査です。AST、ALTは肝臓の細胞に多く含まれ、細胞が壊れたときに血液中に出てくる酵素であり、この値が高いことは肝臓の細胞が壊れていること、つまり肝機能が異常であることを示します。2つの酵素のそれぞれの値とともに、どちらがより高いか(AST/ALT比)も大切です。AST、ALTの異常が指摘された場合は、放置せず、最寄りの医療機関で詳しい検査を受けましょう。そして、肝機能異常の原因がC型肝炎ウイルスによるものか、それとも他の原因によるものかを確認しましょう。C型肝炎ウイルスの感染を確かめるためには、C型肝炎ウイルスの抗体を調べる血液検査を受け、陽性ならウイルス遺伝子を調べる血液検査で再度確認となります。
アルコール性肝硬変とは
アルコール性肝硬変はアルコールが原因となって起こる病気の最終段階と言えるでしょう。日本酒で約5合を毎日20年以上(女性の場合は12~13年)飲み続けた場合、アルコール性肝線維症を経て約10~30%の方が肝硬変に至ると言われてます。
肝硬変の症状は腹水・黄疸を中心として、ひどくなると吐血をしたり昏睡状態に陥ったりすることもあります。
肝硬変になってしまうと治すのは困難と思われている患者さんもいるかもしれませんが、全く回復の余地がないというわけではありません。ただし、飲酒を続けると悪化の一途をたどるのみなので、この時点まで病気が進行した場合は直ちに断酒(一生飲まない)する必要があります。
健康的な飲み方とは
●飲みすぎない
悪酔いや二日酔いをしない酒量、つまり自分の適量を知っておきましょう。アルコールに弱い人は、酒席では早めにウーロン茶などに切り替えることが大切です。女性の場合、生理前はホルモンの関係で酔いやすくなるので、酒量を控えめにしましょう。
●ゆっくり飲む
飲むペースが速いと、それだけ肝臓に負担がかかります。肝臓がアルコールを分解する速度は、日本酒1合(ビール大瓶1本、ワインならグラス2杯)に3~4時間とけっこう時間がかかるからです。日本酒1合を30分以上かけて、ゆっくり飲むようにしましょう。
●おつまみを上手にとる
空腹状態でアルコールを飲むと、吸収が速まり肝臓には大きな負担となります。また、肝臓がアルコールを分解するときに、たんぱく質やビタミン類、ミネラル類が消費されます。そのため、おつまみで大豆食品や野菜・果物、ナッツ類を食べ、上手に栄養補給をしましょう。果物に含まれる果糖には、アルコールの分解を助ける働きもあります。
アルコールには食欲増進効果があるので、つい脂っこいものを食べたくなりますが、脂肪の多い食品も肝臓には負担となります。
●肝臓を休ませる
肝臓はけっこうタフな臓器で、脂肪肝になっていなければ、2日間くらい休ませると機能を回復するといわれます。よく飲む人でも、週に2日はアルコールを飲まない「休肝日」をつくることが大切です。脂肪肝の疑いのある人は、意識的に節酒して肝臓を休ませてください。
関連するまとめ
 takuji
takuji
こんにちわ。
クエン酸と、テニス大好き少年です。プレーするのも、観戦するのも大好きです。
得意なのはフォアストロークです。アプローチから相手を追い込み、ボレーで決めるのが
基本的なスタイルです。苦手なのはバックです。弱点を隠し、なるべくフォアに回り込んで打つ癖で、弱点が余計に目立つようになりました。
これからも、弱点から逃げずにバックを克服していきます。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
スポーツドリンク特集
スポーツドリンク特集

スポーツドリンクの成分について
スポラボ編集部 / 801 view

自家製スポーツドリンクの作り方
スポラボ編集部 / 772 view

水とスポーツドリンクどっちを飲むのがよいのか?
スポラボ編集部 / 821 view