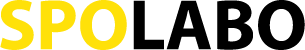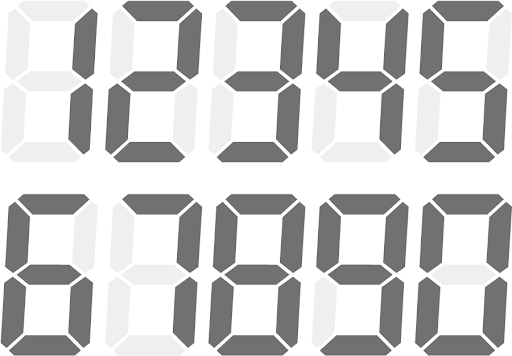BMIの計算方法と判定基準知っておこう
BMIが高いのはもちろん、低すぎる数値も良しとはされていません。
今一度、自身のBMI数値を計算してみて、適正数値との差を確認してみてはいかかでしょうか。
BMIの計算方式
『BMI』とは、体重・体格指数のことで、「体重÷身長÷身長」で算出される体重・体格の指標のこと。
「Body Mass Index」の略称。
従来の「標準体重」などが特に医学的根拠を持たないのに対し、BMI は有疾患率が最も低い点を「理想体重」と設定していることが特徴です。
例えば、身長164cm、体重66kgならば
66 ÷ 1.64 ÷ 1.64 = 24.538… ≒ 24.5
となり、24.5がBMIとなります。
BMIの計算方式は世界共通ですが、結果の数字が示す体型は国によって多少違うようですが、世界保健機関(WHO)の判定基準で数値と体型の関係は以下の通りになります。
16未満痩せすぎ
16.00〜16.99以下痩せ
17.00〜18.49以下痩せぎみ
18.50〜24.99以下普通体重
25.00〜29.99以下前肥満
30.00〜34.99以下肥満(1度)
35.00〜39.99以下肥満(2度)
40.00以上 肥満(3度)
BMIとメタボは関係ある?ない?
肥満という言葉から思いつくのはメタボ。
ただし、内臓脂肪の蓄積とBMIに相関があるとは限りません。
つまり、内臓脂肪が増えたからといって必ずしもBMIが上がるわけではなく、反対にBMIが上がったからといって必ずしも内臓脂肪が増えているわけではありません。
そのため、BMIはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群:通称メタボ)の診断基準としては用いられていません。
ただ、肥満の人の中にメタボ予備軍が潜んでいる可能性を考慮して、特定健診・特定保健指導の対象者を選別する基準にはBMIが用いられているようです。
日本肥満学会のBMI判定基準
日本肥満学会では、BMIが22を適正体重(標準体重)とし、統計的に最も病気になりにくい体重とされています。
25以上を肥満、18.5未満を低体重と分類しています。
BMI数値での判断かこのようになっていました。
18.5未満 低体重(痩せ型)
18.5〜25未満普通体重
25〜30未満肥満(1度)
30〜35未満肥満(2度)
35〜40未満肥満(3度)
40以上 肥満(4度)
WHOとそこまで大きな差はありませんね。
BMIが高いのはもちろん、低すぎる数値も良しとはされていません。
今一度、自身のBMI数値を計算してみて、適正数値との差を確認してみてはいかかでしょうか。
関連するまとめ

満点の星空と海をバックに、野外で映画を楽しめる2日間!野外映画祭「星降る町の映画祭 …
『ピーチガール』『honey』神徳幸治監督、新進気鋭の若手監督・井出内 創&内山 拓也らが手掛ける上映 3 …

すべてのスポーツファンのために!WSC SPORTS LOUNGEをOPEN!
ワールドスポーツコミュニティ株式会社は、同社が運営するWSC SPORTS LOUNGEを名古屋市にOPEN…

スリーツインズ アイスクリームからブランド史上初のダイエットアイス「slim twi…
「Three Twins Ice Cream(スリーツインズアイスクリーム)」は、ブランド史上初のダイエット…
 中山葵
中山葵
スポーツ全般大好きです。
球技は特に大好きで、バスケをよく観戦しています。
今までスポーツは観る専門でしたが、これからは色んなスポーツをやっていきたいと思っています。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
アンケート特集
みんなはどう思っている?

手軽に水分補給!!どんな時にスポーツドリンクを飲む?
スポラボ編集部 / 888 view

水分やミネラルなどを補給できるスポーツドリンク!飲む頻度は?
スポラボ編集部 / 836 view

運動の時の水分補給!!気になるスポーツドリンクの成分とは?
スポラボ編集部 / 888 view