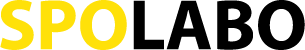10月に行われるお祭りを紹介します。ぜひ見たことがない人はご覧あれ。その23
昼は旧出雲街道を5社の御神輿と10社のだんじりが練り歩き、夜は白熱のだんじり喧嘩で一気に燃え上がります。
久世祭り
久世祭りは岡山県真庭市久世地区で、毎年10月25日と26日にわたって行われるお祭りです。
昼は旧出雲街道を5社の御神輿と10社のだんじりが練り歩き、夜は白熱のだんじり喧嘩で一気に燃え上がります。
だんじりは本来、御神輿の供養のために随行するものですが、今やお祭りの主役になっていると言ってよいと思います。
岡山三大だんじり祭りの一つといわれています。
由来
久世のだんじりの始まりは江戸時代後期。御神輿のように担いでいたことから「担ぎだんじり」と言われていましたが、担いでぶつけ合っていたことでケガ人が絶えず、大正時代中期、馬車台に乗せたことが現在のだんじりの原型です。
昭和30年代まで町の中心を流れる旭川の交通として使われた高瀬舟に由来して、だんじりは船形です。
激しくぶつけ合うだんじり後方は頑丈な鉄板で覆われ、先端の突先は相手のだんじりを突き刺そうとして尖っています。戦時中は鉄板を供出したために鉄道の枕木を尖らせてぶつけ合っていました。
だんじり喧嘩
各社のだんじりは舟形後部の鋭角な部分を鉄板で装甲し、5~7メートル程の距離から、数十人が力の限り突進しぶつけ合う。 だんじりには囃し方(喧嘩囃子を打ち鳴らす)と指揮統制の役員が乗り込み、後部では「てぎ」と呼ばれる舵をとりながら、相手方の側面に自らのだんじりの鋭角な鉄板をぶつけようとする。鉄板のぶつかり合いによって、火花が飛び散ることもある。「だんじり喧嘩」の熱気は、久世の勢いそのものであり、観客の興奮も最高潮に達する。
26日の「だんじり喧嘩」の最後には、各だんじりの屋根に人が登り、全社のだんじりが喧嘩囃子をかき鳴らしながらの餅投げが行われる。その年の祭の最後を飾る「だんじり喧嘩」であり、祭の終わりを惜しみながら、まさに、燃焼し尽すがごとくに熱狂し、フィナーレを迎える。
関連するまとめ

11月に行われるお祭りを紹介します。ぜひ見たことがない人はご覧あれ。その2
11月3日の「練り歩き」では、鬼神「ソバ」「ベタ」「ショーキー」が獅子と共に御輿を先導し、市内を練り歩きます…

半数以上の親が月に「1着以上~3着未満」子ども服購入。1着あたりにかける費用は?
株式会社スタジオアリスは、全国の0歳から2歳の子どもを持つ親500名を対象に「子どものお出かけと服装に関する…
 takuji
takuji
こんにちわ。
クエン酸と、テニス大好き少年です。プレーするのも、観戦するのも大好きです。
得意なのはフォアストロークです。アプローチから相手を追い込み、ボレーで決めるのが
基本的なスタイルです。苦手なのはバックです。弱点を隠し、なるべくフォアに回り込んで打つ癖で、弱点が余計に目立つようになりました。
これからも、弱点から逃げずにバックを克服していきます。
アクセスランキング
人気のあるまとめランキング
アンケート特集
みんなはどう思っている?

水分やミネラルなどを補給できるスポーツドリンク!飲む頻度は?
スポラボ編集部 / 836 view

顔だけじゃない…理想のカラダの男性有名人といえば?
スポラボ編集部 / 830 view

運動の時の水分補給!!気になるスポーツドリンクの成分とは?
スポラボ編集部 / 888 view